![]()
● 去 勢 お よ び 避 妊 に お け る 糸 を 使 わ な い 手 術 法 に つ い て
 去勢や避妊手術を行う際、血管を縛る(結紮)必要があります。その際に使用する糸の種類は、各病院好みやこだわりがあり、これが正しくてこれが正しくないという事は一概にはいえません。しばしばいわれていることは、糸を使用すると、時として糸に反応して肉芽腫と呼ばれる塊ができてしまうことがあるということです。こういった場合には、再手術による肉芽腫および糸の摘出や、長期におよびステロイドの投薬が必要となることがあります。リガシュアシステムにより卵巣動静脈をシーリングおよび切断することで、この部位に肉芽腫が生じるリスクがなくなります。7mmまでの血管をシーリングすることができるため小型犬から大型犬まで適応が可能です。
去勢や避妊手術を行う際、血管を縛る(結紮)必要があります。その際に使用する糸の種類は、各病院好みやこだわりがあり、これが正しくてこれが正しくないという事は一概にはいえません。しばしばいわれていることは、糸を使用すると、時として糸に反応して肉芽腫と呼ばれる塊ができてしまうことがあるということです。こういった場合には、再手術による肉芽腫および糸の摘出や、長期におよびステロイドの投薬が必要となることがあります。リガシュアシステムにより卵巣動静脈をシーリングおよび切断することで、この部位に肉芽腫が生じるリスクがなくなります。7mmまでの血管をシーリングすることができるため小型犬から大型犬まで適応が可能です。
| 手術方法 | 肉芽腫の心配 | 手術時間 |
手術時の安全性の差 |
コスト |
| 糸による手術 | わずかにある | 長い | なし | 安い |
| リガシュアシステム | なし | 短い | なし | 糸よりも高い |
● 去 勢 手 術
去勢手術とは睾丸をとる手術です。通常ワンちゃんにおいては陰嚢(袋)を切ると皮膚炎を起こしたり傷のつきがわるいために睾丸を上位(臍側)に移動して、睾丸のやや上を切開します。猫ちゃんにおいては陰嚢自体を切開します。いずれにおいても切開は1つであり、2つの睾丸を一つの切開ラインから外に出します。体内にはできる限り糸を残さないために外側はおよそ1週間後に抜糸をします。抜糸後2〜3日でシャンプーができるほどに回復いたします。
○ 去 勢 手 術 の メ リ ッ ト
マーキングの予防、おとなしくさせる(凶暴性の減少を含む)、飼いやすくする。という目的で手術を選択されるかたが一番多いように感じます(犬猫共通事項)
前立腺肥大の防止についてですが、老齢になるとほぼすべての個体(90%)に前立腺肥大は生じてきます。しかしながら症状を起こす子はさほど多くはなく(60%)、また症状を起こしてから去勢を行っても効果があります。まれに前立腺肥大による「いきみ」から会陰ヘルニアを起こすこともあります。(ワンちゃんのみ)
肛門周囲腺腫という良性腫瘍がありますが、これは男性ホルモンに依存してできる腫瘍ですので、去勢しておくことで発生を予防することが可能です。(ワンちゃんのみ)
○ 精 巣 の 腫 瘍
セルトリ細胞腫、ライディッヒ細胞腫、セミノーマという3つの腫瘍が生じますが、去勢をしておくことで予防が可能です。(ワンちゃんのみ)
例外として、潜在精巣(お腹に精巣がある=精巣が陰嚢に降りてきていない=陰睾と同義語)の場合には、手術を強くお奨めします。通常、精巣腫瘍は1%とされておりますが、腹腔陰睾の場合には、その発生率が9〜13.6倍上昇するとされております。また鼠径陰睾(お腹ではないが、股間の部分に精巣が存在する場合)の場合には、正常の4倍、腫瘍が発生しやすいとされております。このような場合には、様子を見るのではなく、早めの処置を心がけましょう。
(潜在精巣の診断は満7ヶ月齢の時点で判定するのが良いとされています。)
○ 去 勢 手 術 の デ メ リ ッ ト ①
肥満に注意が必要です。去勢手術を行うことで生体の必要エネルギーが15-20%減少するからとされています。つまり、去勢手術前と同じ量のフードを与えてしますと、必ず太る傾向にあるということになります。ですから、パッケージに書いてある量よりも最低10%、できれば15%ほど減少させた量をあげることが必要です。つまり去勢をしたあとは、6ヶ月齢であっても成犬用あるいは成猫用(1才以上)を使用する、あるいは、肥満犬用あるいは肥満猫用を使用することでたくさん食べて満腹感を得、かつ太りにくいというフードの選択が推奨されます。(犬猫共通事項)
○ 去 勢 手 術 の デ メ リ ッ ト : ★ 猫 ち ゃ ん の み ★
尿道の成長と男性ホルモンは関係するとの学術報告がございます。しかしながら、統計上はまだ確認された事項ではありません。つまりこの学術報告が正しければ早期去勢をした猫ちゃんは尿道の太さが細いために尿が詰まりやすくなる(尿閉)病気にかかりやすくなります。しかし、ほぼ全例で尿閉を起こしている子は肥満であるという事実もあります。つまり、早期去勢により尿道が細いためにこの病気が増加しているのか、去勢をしたために肥満傾向となるためにこの病気が増加しているのかまだわかっておりません。マーキングに関していえば、マーキング行動が生じる前に去勢を行えば、マーキングが出現する確率が圧倒的に低くなるという事実があります。ここで、マーキングの抑制をとるか、尿閉の学術報告をとるかは難しいところではありますが、私の意見としましては、「もし去勢を選択するのであれば、決して肥満させない」という事であると思います。
![]()
● 避 妊 手 術
避妊手術は臍の下を数cm切開します。卵巣を切除するために使用する糸は「サージロン」とよばれる袋毎に滅菌されたナイロン糸を使用します。もしくは前述の「リガシュア」により糸を使用しない手術を行うこともできます。
抜糸は7〜8日後で抜糸後2〜3日でシャンプーを行うことができます。
○ 避 妊 手 術 の メ リ ッ ト
避妊手術はいつ行うべきでしょうか? 初回生理(犬種によって異なりますがおよそ7ヶ月齢~12ヶ月齢の間)が来る前と来た後に手術をするのでは、乳腺腫瘍の発生率に大きな差を生じます。初回発情前に避妊手術を行うことで、将来できるかもしれない乳腺腫瘍の発生率を1/200に減少させることが可能です。しかしながら、1度でも生理が来てしまうと、発生率は1/20まで上昇します。その後、生理が来るたびに1/12 → 1/4〜変化なしに上昇し、その後は発生率は変わらないとされています。以上の理由から当院では6ヶ月齢までに飼主のかたに決定していただくようにお話しております。
また、子宮蓄膿症、卵巣腫瘍は卵巣がなければ生じませんので、何歳で手術を行っても完全な予防が行えます。その他、てんかん発作やアカラス(毛包虫)を現在患っている子では、症状を抑制する効果があります。
もし避妊手術を行わない場合は子供をつくり、繁殖をさせたほうが病気が減少するとされています。
○ 避 妊 手 術 の デ メ リ ッ ト ① : 肥 満
肥満に注意が必要です。避妊手術を行うことで生体の必要エネルギーが15-20%減少するからとされています。つまり、避妊手術前と同じ量のフードを与えてしますと、必ず太る傾向にあるということになります。ですから、パッケージに書いてある量よりも最低10%、できれば15%ほど減少させた量をあげることが必要です。つまり避妊をしたあとは、6ヶ月齢であっても成犬用あるいは成猫用(1才以上)を使用する、あるいは、肥満犬用あるいは肥満猫用を使用することでたくさん食べて満腹感を得、かつ太りにくいというフードの選択が推奨されます。(犬猫共通事項)
○ 避 妊 手 術 の デ メ リ ッ ト ② : 性 格
ほとんどすべての個体では変化いたしません。しかしながら、まれにみる凶暴性などがあり、飼主のかたご自身が身体を噛まれ過去に病院で手術されたなどという場合には、避妊手術は行わないほうが良いでしょう。つまり女性ホルモンは「やさしさ」「おとなしさ」に関与するホルモンであり、これを「切除」してしまうので凶暴性が悪化するわけです。これは特発性凶暴性(原因不明の凶暴性)を有する犬種にあてはまることが多いとされています。通常の場合は心配する必要は全くありません。ほとんど変化がないと思っていただけると良いと思います。
○ 避 妊 手 術 の デ メ リ ッ ト ③ : 失 禁
これも②と同様、滅多にみることはありません。多くの場合は、寝そべって起き上がるとその部位が尿で濡れているといった症状だと思います。正確には「膀胱後方変位症」といいます。「フェニルプロパミン」の投薬により薬剤から離脱しても完全に治癒することもありますし、投薬時だけしか治癒させることができないこともあります。大事なことは、尿失禁というまれにみるデメリットと、非常に多発する乳腺腫瘍や子宮蓄膿症を天秤にかけたときにいずれの重要性が高いか? という事であると思います。 メールで相談する
メールで相談する
● 外 科 料 金
○ 犬 の 避 妊 手 術 ( TAX含む )
術式、安全性などは「外科」の項目をご参照ください
| 犬避妊術 | 犬去勢術 | 猫避妊術 | 猫去勢術 | |
| 1.5kg未満(TAX含) | 51800円 |
35300円 | 43000円 |
26500円 |
| 1.5 〜 5kg未満TAX含) | 49600円 | 32600円 | ||
| 5 〜 10kg未満TAX含) | 51800円 |
35300円 | ||
| 10 〜 14kg未満TAX含) | 59500円 | 37500円 | ||
| 14〜 21kg未満TAX含) | 62800円 | 44650円 | ||
| 21 〜 30kg未満TAX含) | 80500円 | 51800円 | ||
| 30 〜 40kg未満TAX含) | 96000円 | 59500円 |
・上記いずれの手術(猫の去勢を除く)もほとんどのかたは日帰りになりますがご希望により1泊2日も料金は上記と同様になります。リガシュア法を選択された場合、腹部内にイトは残りませんが皮膚は通常通り抜糸が必要となります。
抜糸は7〜10日後となります。上記手術料金には抜糸料金が含まれますので、通常は無料となります。
事前身体検査、麻酔が可能かどうかの血液検査、麻酔、手術、入院、一週間後の再診および抜糸代金
● 麻 酔 の 安 全 性 に つ い て

2025年2月現在、当院で麻酔を行った件数の統計を調べてみました。合計で6484件でした。開業して21年。ただし開業当初は患者様も少なかったので麻酔件数が必ずしも多いとはいえませんでした。現在、全身麻酔を行う件数の統計を調べてみました。
| 全身麻酔件数 | |
| 2024/1/1 〜 2024/12/31 | 290件/年 |
| 2023/1/1 〜 2023/12/31 |
292件/年 |
| 2022/1/1 〜 2022/12/31 | 290件/年 |
| 2021/1/1 〜 2021/12/31 | 267件/年 |
事故の発生率から考えますと2492件で1件の子が亡くなられました。その患者様にとっては歯科の手術。つまりその手術を行うことでより元気でより長く健康でいられることを願って手術されたのですからその気持ち、病院に対する失望感は計り知れないものがあることだと思います。つまり全身麻酔には必ずリスクを伴うのです。当院にも人間のお医者様の患者様が何人もいらっしゃいますが、「そのリスクは完全にはわからない」とお話しされます。つまり医療が発達したことで「もしも」の際に打つ手が増えたといえどもどうしようもない場合というのは存在するということになります。当院は開業してトータルで2件の子が麻酔で亡くなりました(開業21年)。それを高確率とみるか低確率とみるかは患者様によって異なります。手術件数で統計をしてみれば10年に1度というみかたもできるかと思います。
また当院は歯科の手術の件数が多いために一般動物病院様に比較し平均麻酔年齢が非常に高いといえます。逆に考えれば老齢の子の麻酔になれているともいえます。またここ5年くらいは医療機械がだすバイタルサインではなく、「脈」「感覚」というものを一番大事にします。麻酔導入時にかもしだす動物の「様相」、「雰囲気」というものに勝るサインはないと考えています。これは長年の経験によるものでありもっとも重要視しています。
血液検査、エコー、心臓も問題なし。だから麻酔は絶対に大丈夫という安易な考えはしてはいけません。患者様により精神的負担なく全身麻酔をかけていただくにはどうすればよいか? 当院の方向性を一番変えたのは当院の全身麻酔平均年齢をご説明するということです。当院の平均麻酔年齢は9才、10才、11才になります。もちろんそれ以上でも歯周病で顎の骨が折れそうとか、子宮蓄膿症であるとか、どうしても必要な際は何歳であっても全身麻酔はかけます。しかし命にかかわらない問題であれば(たとえば歯をきれいにするだけetc)私の印象ではやはり11才までに全身麻酔を終えた方がよいのではないか?という考えがあります。これは他院からのご紹介、25年の臨床経験で患者様のお話を聞いて感じていることです。つまり12才だ15才だといって、麻酔中に亡くなるとか、麻酔後に目が覚めないなどということはまずないのです。そうではなく、麻酔をかけた後におうちで食事をしなくなったという例を耳にするからです。それは当院で生じたことではないので、他院の病院様がどのような方法で全身麻酔をかけているかが明確にわかっているわけでもなく、他院様を否定することを記載しているわけでは決してありません。なぜなら他院様はその病院のいわゆる「王道」という方法で麻酔をなさっているからです。そのような各病院の適切な麻酔方法であっても、麻酔後に体調が悪くなるのはたいてい12才以降であるというのは私の印象と統計です。これを逸脱していれば全身麻酔をかけないという意味ではございませんが、それが必ず必要な処置でなければ避けてもよいのではないか? という考えもあります。ですから当院では平均が9才、10才、11才ですよ。という話をさしあげて、その年齢という問題点についてきちんと飼い主様が理解し手術をうけるならばそれはひとつの答えですし正しい選択であると思います。もちろんセントバーナードの11才に全身麻酔といわれればそれは違いますので犬種による差はこの文面にはいかされておりませんので適宜、診療の中の飼い主様との話し合いによって決めていく事項だとおもいます。
下記の文章は6、7年前に記載したものです。
泉門の開口しているチワワ(ペコがある)や短頭種(フレンチブルドッグなど)では麻酔に弱い、麻酔が危険という情報がネットなどでも多く流れております。たしかに、安易に選択した麻酔薬でチワワに麻酔をかけたり、管理不足による短頭種の麻酔、サイトハウンド(イタグレ)など筋肉量の少ない犬種での麻酔大量急速投与を行うことは危険です。したがって、安易な麻酔選択や管理に より世の中には麻酔事故が起きてしまっている例が少数ながらあるのかもしれません。こういった情報が増幅されて、これらの犬種に麻酔をかけるのは危険であるという情報が非常に一般化されてしまったのかと思います。その導入の際に生じる問題点に関して、当院では生じる事を前提に薬剤を用意しており、そこに対処することですべて問題なく手術終了しております。手技、経験、麻酔薬の選択に誤りをおかさなければこれらの犬種に麻酔をかけることと他の犬種に麻酔をかけることにおける安全性は同一と考えていただいてかまいません。また麻酔薬は体表面積あるいは体重で量を決定するわけですから、小さいから危険という事はありません。
肝臓、腎臓、心臓、肺の問題。この4つの臓器が健常であること。それに加え、中高齢動物では、心臓病、糖尿病、甲状腺機能低下症、クッシング症候群。この4つのうちひとつでも罹患していれば麻酔のリスクは上昇します。
当院では術前の血液検査、最新のモニター機器とイソフルレン麻酔により極めて安全な麻酔方法を行っております。また私(院長)がすべて導入および気管挿管を行うようにしております。老齢時疾患時にも、プロポフォール&アクトシン麻酔法を使用し、より体に配慮した麻酔方法を行っております。高齢であれば術前点滴、術前酸素投与をおこなったあとに、きわめて緩除に麻酔を導入し、維持麻酔に切り替えます。また術中点滴も行い、腎臓への負担を軽減するするようにしております。術後の覚醒が悪い場合には、酸素室にいれ状態の安定をまちます。総合的に考え現在では人間と同等のリスクと考えます。 メールで相談する
手術をご希望の際には上記をご了承の上、手術を依頼してください。また手術予約表を受領された患者様は上記を理解されたことといたします。
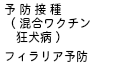
 H O M E
H O M E 避 妊 と 去 勢
避 妊 と 去 勢 レ ー ザ ー 手 術 と は
レ ー ザ ー 手 術 と は